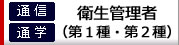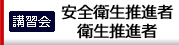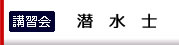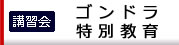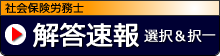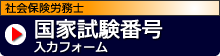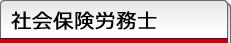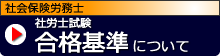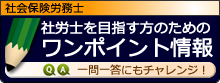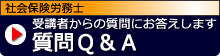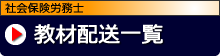��ʍ��c�@�l�@���S�q�����y�Z���^�[�͎ИJ�m�E�q���Ǘ��ғ��̎��i�擾���T�|�[�g���܂��B�i���t�{�F�j
TEL. 03-5979-9750
E-mail. jimu@lejlc.co.jp
�ИJ�m�����@���i��ɂ���
�ߘa7�N�i��57��j�ИJ�m�����̌��ʂƑ���
�ߘa7�N�i��57��j�Љ�ی��J���m�����͂���8��24���i���j�A�S����v19�s���{���̉��ōs���܂������A���̌��ʂ��A10��1���i���j�Ɋ���y�ёS���Љ�ی��J���m��A����̎ИJ�m�����Z���^�[�z�[���y�[�W��Ŕ��\����܂����B ���̎��{�T���́A�ȉ��̂Ƃ���ł��B���{�T��
| ���� | �ߘa7�N���� | �ΑO�N�� | �ߘa6�N |
|---|---|---|---|
| �\���Ґ� | 53,618�l | -89�l | 53,707�l |
| �Ґ� | 43,421�l | +247�l | 43,174�l |
| �� | 81.0% | +0.6�|�C���g | 80.4% |
| ���i�Ґ� | 2,376�l | -598�l | 2,974�l |
| ���i�� | 5.5% | -1.4�|�C���g | 6.9% |
���i��_
�i�P�j���i�
�{�N�x�̍��i��́A����2�̏������������̂����i�Ƃ���B
�@ �I���������́A�����_22�_�ȏォ�e�Ȗ�3�_�ȏ�ł����
�i�������A�J���ҍЊQ�⏞�ی��@�A�J���Ǘ����̑��̘J���Ɋւ����ʏ펯�y�юЉ�ی��Ɋւ����ʏ펯��2�_�ȏ�j
�A ���ꎮ�����́A�����_42�_�ȏォ�e�Ȗ�4�_�ȏ�ł����
�i�������A�ٗp�ی��@��3�_�ȏ�j
����L���i��́A�����̓�Փx�ɍ������������Ƃ���A��N�x�����̍��i����������̂ł���B
�i�Q�j�z�_
�@ �I���������́A�e��1�_�Ƃ��A1�Ȗ�5�_���_�A���v40�_���_�Ƃ���B
�A ���ꎮ�����́A�e��1�_�Ƃ��A1�Ȗ�10�_���_�A���v70�_���_�Ƃ���B
���]
�i�P�j�ߘa7�N�����i��57��j�̍��i���́A�u5.5���v�i�O�N����1.4�|�C���g�ቺ�j
�Љ�ی��J���m�����i�ȉ��A�u�ИJ�m�����v�j�̍��i���́A����20�N�i��40��j���畽��26�N�i��46��j�̎����܂ŁA
1����̌㔼�i5.4���`9.3���j�Ő��ڂ��Ă��܂������A����27�N�i��47��j�Ɏ����j��Œ�ŁA���߂�5�����u2.6���v���L�^���܂����B
����ɁA���N�̕���28�N�i��48��j������27�N�Ɏ����j��2�ԖڂɒႢ�u4.4���v�ɂƂǂ܂������Ƃ���A�ИJ�m�����́A5���������u�ፇ�i������v�ɓ��������̂Ƃ݂��Ă��܂����B
�������A����29�N�i��49��j�̎����ł́A�u6.8���v��3�N�Ԃ�Ɂu5���v��傫�������A��������30�N�i��50��j�i6.3���j�A�ߘa���N�i��51��j�i6.6���j�A�ߘa2�N�i��52��j�i6.4���j��4�N�A��6������L�^���܂����B �ߘa3�N�i��53��j�̍��i���͂���ɏ㏸���A�ߋ�10�N�ł́A����26�N�́u9.3���v�Ɏ����A2�Ԗڂɍ����u7.9���v���L�^���Ă��܂��B �ߘa4�N�i��54��j�̎����ł́A�u5.3���v��6�N�Ԃ��6���������ፇ�i���ƂȂ�܂������A�ߘa5�N�i��55��j�y�їߘa6�N(��56��)�̎����̍��i���́A���ꂼ��u6.4���v�A�u6.9���v��6����ɕ������Ă��܂��B
���̂悤�ȗ��ꂩ��A�吨�Ƃ��āA�u���i���v�́A�u6����v�̈�����ɓ��������̂ƍl�����܂������A����̗ߘa7�N�i��57��j�����̍��i���́A�O�N����1.4�|�C���g�̒ቺ�ƂȂ�u5.5���v�Ɣ��\����܂����B ���́u5.5���v�Ƃ������i���́A����29�N�i��49��j�̎����ȍ~�ł́A�ߘa4�N�i��54��j�́u5.3���v�Ɏ����u�ፇ�i���v�ƂȂ��Ă��܂��B
�������A�ŋ߂̎����ł́A�u���N��1�x�v�̕p�x�ŁA�u�ፇ�i���v���L�^����N��������̂́A�ፇ�i�������N�ȍ~���p�����邱�Ƃ͔�r�I���Ȃ����߁A ����̌��ʂ́A�u�ፇ�i������̍ė��v�ƍl��������A�u���N��1�x�L�^�����ፇ�i���̔N�v�ł������ƍl����̂��Ó���������܂���B ���̂悤�ȗ��ꂩ��A�ИJ�m�����̍��i����\�z����ƁA�u�ፇ�i���v���L�^��������̎����́u���N�v�Ɏ��{�����ߘa8�N�i��58��j�̎����ł́A���i���́u6���v��ɕ�������\������荂�����̂ƍl�����܂��B
����̎����ɂ����鍇�i�Ґ��́A�u2,376�l�v�ŁA�O�N�́u2,974�l�v�Ɣ�ׁu598�l�v�������Ă��܂��B����̎Ґ��i43,421�l�j�́A�O�N�i43,174�l�j�Ɣ��247�l�������Ă��܂����A �Ґ����u�{1.0���v�Ƒ��������ɂ�������炸�A���i�Ґ��́u�|7.9���v�Ƒ傫���������Ă��܂��̂ŁA ����́u���i�Ґ��v�̌����̍ő�̗v���́A���i���i5.5���j���O�N�i6.9���j�Ɣ�r����1.4�|�C���g�ቺ�������Ƃɂ������悤�ł��B
�Ȃ��A���i�Ґ��̐��ڂ��݂�ƁA����26�N�ȑO��10�N�Ԃ̕��ς̍��i�Ґ��̖�4,000�l�Ɣ�r����ƁA����̍��i�Ґ���1,600�l���x�������Ă��܂��B ����́A�ИJ�m�̎Ґ����s�[�N���i����22�N�E55,445�l�j�Ɣ�r���āA����̎����i43,421�l�j�ł�1��2,000�l���A�������Ă��邱�Ƃ��v���ƂȂ��Ă��܂��B
�������A����29�N�i��49��j�̎����ł́A�u6.8���v��3�N�Ԃ�Ɂu5���v��傫�������A��������30�N�i��50��j�i6.3���j�A�ߘa���N�i��51��j�i6.6���j�A�ߘa2�N�i��52��j�i6.4���j��4�N�A��6������L�^���܂����B �ߘa3�N�i��53��j�̍��i���͂���ɏ㏸���A�ߋ�10�N�ł́A����26�N�́u9.3���v�Ɏ����A2�Ԗڂɍ����u7.9���v���L�^���Ă��܂��B �ߘa4�N�i��54��j�̎����ł́A�u5.3���v��6�N�Ԃ��6���������ፇ�i���ƂȂ�܂������A�ߘa5�N�i��55��j�y�їߘa6�N(��56��)�̎����̍��i���́A���ꂼ��u6.4���v�A�u6.9���v��6����ɕ������Ă��܂��B
���̂悤�ȗ��ꂩ��A�吨�Ƃ��āA�u���i���v�́A�u6����v�̈�����ɓ��������̂ƍl�����܂������A����̗ߘa7�N�i��57��j�����̍��i���́A�O�N����1.4�|�C���g�̒ቺ�ƂȂ�u5.5���v�Ɣ��\����܂����B ���́u5.5���v�Ƃ������i���́A����29�N�i��49��j�̎����ȍ~�ł́A�ߘa4�N�i��54��j�́u5.3���v�Ɏ����u�ፇ�i���v�ƂȂ��Ă��܂��B
�������A�ŋ߂̎����ł́A�u���N��1�x�v�̕p�x�ŁA�u�ፇ�i���v���L�^����N��������̂́A�ፇ�i�������N�ȍ~���p�����邱�Ƃ͔�r�I���Ȃ����߁A ����̌��ʂ́A�u�ፇ�i������̍ė��v�ƍl��������A�u���N��1�x�L�^�����ፇ�i���̔N�v�ł������ƍl����̂��Ó���������܂���B ���̂悤�ȗ��ꂩ��A�ИJ�m�����̍��i����\�z����ƁA�u�ፇ�i���v���L�^��������̎����́u���N�v�Ɏ��{�����ߘa8�N�i��58��j�̎����ł́A���i���́u6���v��ɕ�������\������荂�����̂ƍl�����܂��B
����̎����ɂ����鍇�i�Ґ��́A�u2,376�l�v�ŁA�O�N�́u2,974�l�v�Ɣ�ׁu598�l�v�������Ă��܂��B����̎Ґ��i43,421�l�j�́A�O�N�i43,174�l�j�Ɣ��247�l�������Ă��܂����A �Ґ����u�{1.0���v�Ƒ��������ɂ�������炸�A���i�Ґ��́u�|7.9���v�Ƒ傫���������Ă��܂��̂ŁA ����́u���i�Ґ��v�̌����̍ő�̗v���́A���i���i5.5���j���O�N�i6.9���j�Ɣ�r����1.4�|�C���g�ቺ�������Ƃɂ������悤�ł��B
�Ȃ��A���i�Ґ��̐��ڂ��݂�ƁA����26�N�ȑO��10�N�Ԃ̕��ς̍��i�Ґ��̖�4,000�l�Ɣ�r����ƁA����̍��i�Ґ���1,600�l���x�������Ă��܂��B ����́A�ИJ�m�̎Ґ����s�[�N���i����22�N�E55,445�l�j�Ɣ�r���āA����̎����i43,421�l�j�ł�1��2,000�l���A�������Ă��邱�Ƃ��v���ƂȂ��Ă��܂��B
�i�Q�j���ꎮ�����̍��i��_�́A�O�N��2�_�����u42�_�v
����̑��ꎮ�����̑S�҂̕��ϓ_�i�����Z���^�[���\�B�ȉ��A�����B�j�́A�u28.4�_�v�ŁA�O�N�i30.6�_�j�����u2.2�_�v������Ă��܂��B
����̑��ꎮ�̎����ł́A�e�Ȗڂɂ��āA��₪�����o�肳��A�S�̓I�Ȗ��̃��x���́A���߂�5�N�Ԃ̎����̒��ł��A�ł���x�������������̂ƍl�����܂��B
�Ȃ��A�O�q�̂悤�ɁA����̑��ꎮ�̕��ϓ_�́A�O�N�̕��ϓ_�Ƃ̔�r�ł́A�u2.2�_�v�Ⴉ�������Ƃ���A����̑��ꎮ�̑������_�́u���i��_�v�́A�O�N�i�u44�_�v�j��2�_�����u42�_�v�Ɣ��\����܂����B ���́u42�_�v�́A����23�N�i��43��j�����ȍ~�ł́A����28�N�i��48��j�ƕ��сA�ł��Ⴂ�u���i��_�v�ƂȂ��Ă��܂��B �܂��A����30�N�i��50��j�̎����ȍ~�A�ߘa6�N�i��56��j�̎����܂ōs���Ă��Ȃ������u�Ȗڕʁv�́u3�_�̋~�ϑ[�u�v���A����̎����ł́u�ٗp�ی��@�v�ōs��ꂽ���Ƃ�����A ����́u���ꎮ�����v�́A����29�N�i��49��j�̎����ȍ~�ł́A�u�ł���x�̍����v��肪�o�肳�ꂽ���̂ƍl�����܂��B
���Ȃ݂ɁA���߂�6�N�Ԃ́u���ꎮ�̍��i��_�v�Ɓu�S�҂̑��ꎮ�̕��ϓ_�v���r����ƁA�ߘa2�N�i31.5�_�i�S�҂̑��ꎮ�̕��ϓ_�B�ȉ������j��44�_�i���i��_�B�ȉ������j�j�A �ߘa3�N�i32.3�_��45�_�j�A�ߘa4�N�i30.9�_��44�_�j�A�ߘa5�N�i31.8�_��45�_�j�A�ߘa6�N�i30.6�_��44�_�j�A�ߘa7�N�i28.4�_��42�_�j�ƂȂ��Ă���A �u���ꎮ�̍��i��_�v�́A�u�S�҂̑��ꎮ�̕��ϓ_�v�ɔ�Ⴕ�Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
���̂��߁A�ߘa8�N�̑��ꎮ�́u���i��_�v�ɂ��Ă��A���R�̂��ƂȂ���A���̓�Փx�i�҂̕��ϓ_�j�ɔ�Ⴕ�Č��肳�����̂ƍl�����A�u�����_�ȏ���A���S���v�Ƃ������z�肷�邱�Ƃ͓���悤�ł��B
�Ȃ��A�O�q�̂悤�ɁA����̑��ꎮ�̕��ϓ_�́A�O�N�̕��ϓ_�Ƃ̔�r�ł́A�u2.2�_�v�Ⴉ�������Ƃ���A����̑��ꎮ�̑������_�́u���i��_�v�́A�O�N�i�u44�_�v�j��2�_�����u42�_�v�Ɣ��\����܂����B ���́u42�_�v�́A����23�N�i��43��j�����ȍ~�ł́A����28�N�i��48��j�ƕ��сA�ł��Ⴂ�u���i��_�v�ƂȂ��Ă��܂��B �܂��A����30�N�i��50��j�̎����ȍ~�A�ߘa6�N�i��56��j�̎����܂ōs���Ă��Ȃ������u�Ȗڕʁv�́u3�_�̋~�ϑ[�u�v���A����̎����ł́u�ٗp�ی��@�v�ōs��ꂽ���Ƃ�����A ����́u���ꎮ�����v�́A����29�N�i��49��j�̎����ȍ~�ł́A�u�ł���x�̍����v��肪�o�肳�ꂽ���̂ƍl�����܂��B
���Ȃ݂ɁA���߂�6�N�Ԃ́u���ꎮ�̍��i��_�v�Ɓu�S�҂̑��ꎮ�̕��ϓ_�v���r����ƁA�ߘa2�N�i31.5�_�i�S�҂̑��ꎮ�̕��ϓ_�B�ȉ������j��44�_�i���i��_�B�ȉ������j�j�A �ߘa3�N�i32.3�_��45�_�j�A�ߘa4�N�i30.9�_��44�_�j�A�ߘa5�N�i31.8�_��45�_�j�A�ߘa6�N�i30.6�_��44�_�j�A�ߘa7�N�i28.4�_��42�_�j�ƂȂ��Ă���A �u���ꎮ�̍��i��_�v�́A�u�S�҂̑��ꎮ�̕��ϓ_�v�ɔ�Ⴕ�Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
���̂��߁A�ߘa8�N�̑��ꎮ�́u���i��_�v�ɂ��Ă��A���R�̂��ƂȂ���A���̓�Փx�i�҂̕��ϓ_�j�ɔ�Ⴕ�Č��肳�����̂ƍl�����A�u�����_�ȏ���A���S���v�Ƃ������z�肷�邱�Ƃ͓���悤�ł��B
�i�R�j�I���������́u�J�Еی��@�v�A�u�J���̏펯�v�A�u�Љ�̏펯�v�Łu2�_�v�̋~�ϑ[�u
����̑I�����̎҂̑������_�̕��ϓ_�́A�u20.3�_�v�ŁA�ߘa6�N�́u22.9�_�v���u2.6�_�v�A�ߘa5�N�́u23.3�_�v���u3.0�_�v������Ă��܂��B
�ߘa7�N�̑I�����̑������_�̍��i��_�́A�ߘa6�N�́u25�_�v����u3�_�v�A�ߘa5�N�́u26�_�v����u4�_�v�A���ꂼ������������A�u22�_�v�Ɣ��\����Ă��܂��B
����́u���i��_�i22�_�j�v���A�ߘa6�N�y�їߘa5�N�̍��i��_�i�u25�_�v�A�u26�_�v�j�Ɣ�r����ƁA�O�q�̍���̎҂̕��ϓ_�Ɨߘa6�N�y�їߘa5�N�̕��ϓ_�̓��_���i-2.6�`-3.0�_�j�ȏ�̈����������s��ꂽ���ƂɂȂ�܂��B
����́A���ϓ_�̓��_���ȏ�ɁA����́A�e�Ȗڂ̍��i�_�Ƃ����u3�_�ȏ�̓��_�ҁv�̊������Ⴉ�������Ƃ��v���ƍl���炦�܂��B
�I���������̍��i��ɂ��ẮA�u�������_�v�̂ق��ɁA�����Ƃ��āA�e�Ȗځu3�_�ȏ�v���u���i��v�Ƃ��Ă��܂�(���ۂɂ́A�u�Ȗڕʁv�̍��i��_���N���A�����҂��u�������_�v�ō��i��_������邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B)�B �������A�u3�_�ȏ�v�̓��_�҂̊������Ⴉ�����Ȗڂɂ��ẮA�u2�_�v�i����Ɂu2�_�ȏ�v�̓��_�҂̊������Ⴉ�����Ȗڂɂ��Ắu1�_�v�j�̓��_�̉Ȗڂ����i�_�Ƃ��ċ~�ς��Ă��܂��B
�ߘa3�N�܂ŁA�قƂ�ǂ̔N�ōs���Ă����u2�_�i1�_�j�v�̋~�ϑ[�u�́A�ߘa4�N�y�їߘa5�N��2�N�Ԃ̎����ł͑ΏۉȖڂ�1�Ȗڂ��Ȃ��A�ߘa6�N�̎����ł́A�u�J���Ɋւ����ʏ펯�v��1�Ȗڂ݂̂��u2�_�v�̋~�ϑ[�u�̑ΏۂƂȂ�܂����B ���̂悤�ɁA�ŋ߂̎����ł́A�w�e�Ȗځu3�_�ȏ�v���邱�Ɓx�̍��i��̌��i�������܂�A�u2�_�̋~�ς͋ɗ͔F�߂Ȃ��v�Ƃ����X�����݂��Ă��܂����B ���Ђł��A����́u2�_�̋~�ς�1�Ȗڂ��s���Ȃ��\��������v�Ɨ\�z���A�~�ς̉\��������ȖڂƂ��āA �u2�_�ȉ��v�̓��_�҂̊����������Ɨ\�z���ꂽ�@�u�J�Еی��@�v�A�A�u�J���Ɋւ����ʏ펯�v�y�чB�u�Љ�ی��Ɋւ����ʏ펯�v�ɂ��ẮA ���ꂼ��A�u3���v�A�u5���v�A�u3���v���x�̊m���Łu2�_�v�̋~�ς̉\�������邱�Ƃ��w�E���܂����B
���\���ꂽ���ʂɂ��ƁA���Ђ��w�E����3�ȖڂƂ��Ɂu�~�ϑ[�u�v�̑ΏۂƂȂ�܂������A����́A�҂̕��ϓ_���A�@���u2.1�_�v�A�A���u2.0�_�v�A�B���u1.9�_�v�Ŕ��ɒႭ�A ������3�Ȗڂɂ��āu2�_�v�̋~�ς��s�����ƂŁA�u���i���v�̐����̈ێ��i�O�q�̂悤�ɁA3�Ȗڂ̋~�ς��s���Ă��A�Ȃ��A�u���i���v�͑O�N����1.4�|�C���g�ቺ���Ă��܂��j��}�������̂ƍl�����܂��B
�Ȃ��A�O�q�́u�I�����v�́w�e�Ȗځu3�_�ȏ�v���邱�Ɓx�̍��i��̌��i���́A������ێ��������̂Ɨ\�z����A����́u3�Ȗځv�ōs��ꂽ�u2�_�v�̋~�ς́A �����܂ł��u�ɒ[�Ɂu3�_�ȏ�̓��_�҂̊������Ⴉ�����v���Ƃɂ�����v�ɂ��[�u�ƍl���A�ߘa8�N�x�̎҂̕��ɂ́A�u2�_�̋~�ς͍s���Ȃ��v���Ƃ�O��Ƃ����u�I������v���K�v�ł��B
�I���������̍��i��ɂ��ẮA�u�������_�v�̂ق��ɁA�����Ƃ��āA�e�Ȗځu3�_�ȏ�v���u���i��v�Ƃ��Ă��܂�(���ۂɂ́A�u�Ȗڕʁv�̍��i��_���N���A�����҂��u�������_�v�ō��i��_������邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B)�B �������A�u3�_�ȏ�v�̓��_�҂̊������Ⴉ�����Ȗڂɂ��ẮA�u2�_�v�i����Ɂu2�_�ȏ�v�̓��_�҂̊������Ⴉ�����Ȗڂɂ��Ắu1�_�v�j�̓��_�̉Ȗڂ����i�_�Ƃ��ċ~�ς��Ă��܂��B
�ߘa3�N�܂ŁA�قƂ�ǂ̔N�ōs���Ă����u2�_�i1�_�j�v�̋~�ϑ[�u�́A�ߘa4�N�y�їߘa5�N��2�N�Ԃ̎����ł͑ΏۉȖڂ�1�Ȗڂ��Ȃ��A�ߘa6�N�̎����ł́A�u�J���Ɋւ����ʏ펯�v��1�Ȗڂ݂̂��u2�_�v�̋~�ϑ[�u�̑ΏۂƂȂ�܂����B ���̂悤�ɁA�ŋ߂̎����ł́A�w�e�Ȗځu3�_�ȏ�v���邱�Ɓx�̍��i��̌��i�������܂�A�u2�_�̋~�ς͋ɗ͔F�߂Ȃ��v�Ƃ����X�����݂��Ă��܂����B ���Ђł��A����́u2�_�̋~�ς�1�Ȗڂ��s���Ȃ��\��������v�Ɨ\�z���A�~�ς̉\��������ȖڂƂ��āA �u2�_�ȉ��v�̓��_�҂̊����������Ɨ\�z���ꂽ�@�u�J�Еی��@�v�A�A�u�J���Ɋւ����ʏ펯�v�y�чB�u�Љ�ی��Ɋւ����ʏ펯�v�ɂ��ẮA ���ꂼ��A�u3���v�A�u5���v�A�u3���v���x�̊m���Łu2�_�v�̋~�ς̉\�������邱�Ƃ��w�E���܂����B
���\���ꂽ���ʂɂ��ƁA���Ђ��w�E����3�ȖڂƂ��Ɂu�~�ϑ[�u�v�̑ΏۂƂȂ�܂������A����́A�҂̕��ϓ_���A�@���u2.1�_�v�A�A���u2.0�_�v�A�B���u1.9�_�v�Ŕ��ɒႭ�A ������3�Ȗڂɂ��āu2�_�v�̋~�ς��s�����ƂŁA�u���i���v�̐����̈ێ��i�O�q�̂悤�ɁA3�Ȗڂ̋~�ς��s���Ă��A�Ȃ��A�u���i���v�͑O�N����1.4�|�C���g�ቺ���Ă��܂��j��}�������̂ƍl�����܂��B
�Ȃ��A�O�q�́u�I�����v�́w�e�Ȗځu3�_�ȏ�v���邱�Ɓx�̍��i��̌��i���́A������ێ��������̂Ɨ\�z����A����́u3�Ȗځv�ōs��ꂽ�u2�_�v�̋~�ς́A �����܂ł��u�ɒ[�Ɂu3�_�ȏ�̓��_�҂̊������Ⴉ�����v���Ƃɂ�����v�ɂ��[�u�ƍl���A�ߘa8�N�x�̎҂̕��ɂ́A�u2�_�̋~�ς͍s���Ȃ��v���Ƃ�O��Ƃ����u�I������v���K�v�ł��B
�i�S�j��57��Љ�ی��J���m�����̑���
����̎����ɂ��āA�@�u���i���v�A�A�u���ꎮ�̍��i��_�v�A�B�u�I�����́u2�_�i1�_�j�v�̋~�ς̑ΏۂƂȂ�����萔�v�����A
���߂�5�N�Ԃ̎����Ɣ�r���A�ߘa8�N�̎����ɂ��Ă̇@�`�B��\�z����ƈȉ��̂Ƃ���ł��B
�@�̍��i���ɂ��ẮA2�N�������u6���v�䂩��A����u5���v��ɒቺ���܂������A���N�̍��i���́A���̔N�̑��ꎮ�y�ёI�����́u���i��_�v�ɂ���č��E����܂��B
�O�L�i�P�j�̍��ł́A�ߘa8�N�̍��i���ɂ��āA�u6���v��ɖ߂�\���������Ƃ̗\�z�����܂������A���ꎮ�́u���i��_�v�̂킸��1�_�̍��A
�I������2�_�̋~�ϑ[�u�̑ΏۂƂȂ�Ȗڐ���1�Ȗڂ̍��ɂ���āA���i�����傫���㉺���܂��̂ŁA���i����\�z���邱�Ƃ͎���ł��B
���̂��߁A�ߘa8�N�x�̎��i�߂�ɓ������ẮA�u���i���v��z�肷��̂ł͂Ȃ��A��r�I�A�����͈͂̓��_�̒��Ő��ڂ���u���i��_�v���N���A���邽�߂̊w�K�ɓO���邱�Ƃ��K�v�ł��B
�A�̑��ꎮ�̍��i��_�ɂ��ẮA�O�L�i�Q�j�̍��ŏq�ׂ��悤�ɁA���̔N�̎҂̕��ϓ��_�ɔ�Ⴕ�����_�Ō��肳��Ă��܂��̂ŁA
�ߘa8�N�����́u���i��_�v�́A���̔N�́u���̃��x���v�ɍ��E�����v�f���傫���A�����_�ŗ\�z���邱�Ƃ͍���ł����A
����́u���i��_�v�ƂȂ����u42�_�v����2�`3�_�����u44�`46�_�v���x�̓��_��ڕW�ɑ��ꎮ����s�����Ƃ��Ó��ł���悤�ł��B
�B�̑I�����́u2�_�v�̋~�ϑ[�u�̉\���ɂ��Ă��A���ꎮ�����Ɠ��l�A�������̃��x���ɂ��~�ς̑ΏۉȖڂ��ς��܂��B
�O�L�i�R�j�̍��ŏq�ׂ��悤�ɁA����̎����ŁA3�ȖڂŁu2�_�v�̋~�ϑ[�u���s��ꂽ���Ƃ́A�����܂ł��u��O�v�ƍl���A�ߘa8�N�����̑I��������s���ɂ������ẮA�u2�_�̋~�ς͍s���Ȃ��v���Ƃ�O��Ƃ����u3�_�ȏ�̐�Ίm�ہv��ڕW�Ƃ������Ƃ���ł��B
����12�N�ȍ~�̎ИJ�m�����̎��{��
�����s�́u�I���������v���̗p���ꂽ����12�N�ȍ~�̎ИJ�m�����̎��{�ɂ��Čf�����Ă��܂��B
| �N | ���ꎮ���� | �I�������� | ���i�� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� ���i ��_ |
�ȖڕʕK�v�Œᓾ�_ | ��Փx | ����� ���i ��_ |
�ȖڕʕK�v�Œᓾ�_ | ��Փx | ||
| 7�N | 42�_ | 4�_ �@�@�@(��ٗp���3�_�j |
A | 22�_ | 3�_ �@(��J�У���J�꣥��Ј�2�_�j |
A | 5.5% |
| 6�N | 44�_ | 4�_ | A | 25�_ | 3�_ �@�@�@(��J�ꣁ�2�_�j |
B | 6.9% |
| 5�N | 45�_ | 4�_ | B | 26�_ | 3�_ | B | 6.4% |
| 4�N | 44�_ | 4�_ | A | 27�_ | 3�_ | C | 5.3% |
| 3�N | 45�_ | 4�_ | B | 24�_ | 3�_ (��J�ꣁ�1�_�E�u���N�v��2�_�j |
A | 7.9% |
| 2�N | 44�_ | 4�_ | B | 25�_ | 3�_ �@(�u�J��v���Ј꣥����ۣ��2�_�j |
A | 6.4% |
| ���N | 43�_ | 4�_ | A | 26�_ | 3�_ �@�@�@(��Јꣁ�2�_�j |
C | 6.6% |
| 30�N | 45�_ | 4�_ | B | 23�_ | 3�_ �@(��Ј꣥����N���2�_�j |
B | 6.3% |
| 29�N | 45�_ | 4�_ �@�@�@(����N���3�_�j |
B | 24�_ | 3�_ �@(��ٗp������ۣ��2�_�j |
B | 6.8% |
| 28�N | 42�_ | 4�_ �@(�u�펯������N���u���N�v ��3�_�j |
A | 23�_ | 3�_ �@(��J��������ۣ��2�_�j |
A | 4.4% |
| 27�N | 45�_ | 4�_ | A | 21�_ | 3�_ �@(��J������Џ�������ۣ� �@����N���2�_�j |
A | 2.6% |
| 26�N | 45�_ | 4�_ �@�@�@(��펯���3�_�j |
B | 26�_ | 3�_ �@(��ٗp������ۣ��2�_�j |
C | 9.3% |
| 25�N | 46�_ | 4�_ | B | 21�_ | 3�_ (��Џ����1�_ ��J�У���ٗp������ۣ��2�_�j |
A | 5.4% |
| 24�N | 46�_ | 4�_ | B | 26�_ | 3�_ �@�@�@(����N���2�_�j |
B | 7.0% |
| 23�N | 46�_ | 4�_ | B | 23�_ | 3�_ (��J���q����J�У���Џ�������N������N���2�_�j |
A | 7.2% |
| 22�N | 48�_ | 4�_ | B (��) |
23�_ | 3�_ (����N���1�_ ����ۣ�����N����Џ����2�_�j |
A | 8.6% |
| 21�N | 44�_ | 4�_ | B | 25�_ | 3�_ (��J���q����J������N���2�_) |
B | 7.6% |
| 20�N | 48�_ | 4�_ | C | 25�_ | 3�_ (����ۣ��1�_ ����N������N���2�_) |
A | 7.5% |
| 19�N | 44�_ | 4�_ | B | 28�_ | 3�_ | C | 10.6% |
| 18�N | 41�_ | 4�_ (��J���q����펯���3�_) |
A | 22�_ | 3�_ (��J���q����J�У���Џ�������N���2�_) |
A | 8.5% |
| 17�N | 43�_ | 4�_ | B | 28�_ | 3�_ �@�@(��J���q���2�_) |
B | 8.9% |
| 16�N | 42�_ | 4�_ (����ۣ�����N������N���3�_) |
A | 27�_ | 3�_ �@�@�@(����ۣ��1�_) |
B | 9.4% |
| 15�N | 44�_ | 4�_ (��J���q������N���3�_) |
B | 28�_ | 3�_ (��J������ИJ������N������N���2�_) |
A | 9.2% |
| 14�N | 44�_ | 4�_ | B | 28�_ | 3�_ �@�@(��J���q���2�_) |
B | 9.3% |
| 13�N | 45�_ | 4�_ �@�@�@(��펯���3�_) |
B | 26�_ | 3�_ (��J���q������N������N���2�_) |
A | 8.7% |
| 12�N | 49�_ | 4�_ | C | 28�_ | 3�_ | C | 8.6% |
�i���j
1�D�u��Փx�v�iA����x�������AB�����ʁAC����x���Ⴂ�j�́A�e�N�x�ɂ����Ď҂����ꂽ�����̓��_�y�ю����Z���^�[���\�́u�Љ�ی��J���m�������_�v�ɂ��B
2�D�u���ꎮ�v��70�_���_�i1�Ȗ�10�_���_�j�A�u�I�����v��40�_���_�i1�Ȗ�5�_���_�j�B
3�D����22�N�̑��ꎮ�����̓�Փx�́uB�v�ł��������A���̔N�͏o��~�X��5�₠��A�҂ɗL���ȍ̓_���s��ꂽ���߁A��背�x���Ɣ�r���āA�u���i��_�v�������Ȃ����B