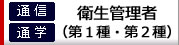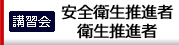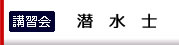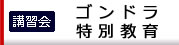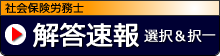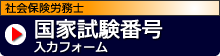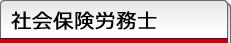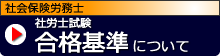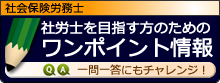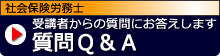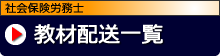一般財団法人 安全衛生普及センターは社労士・衛生管理者等の資格取得をサポートします。(内閣府認可)
TEL. 03-5979-9750
E-mail. jimu@lejlc.co.jp
令和7年社労士試験の総括と合格予想基準
さる8月24日に行われた令和7年(第57回)社会保険労務士試験について、当センターに寄せられた試験当日の復元解答の分析結果をもとに、試験の総評と合格予想基準をまとめました。
なお、例年のことですが、復元解答をお寄せいただいている方々は、合格基準の目安点を確保しているか、あるいは合否のボーダーライン上にある方が多く、以下の平均得点等のデータは、全受験者の平均より上位に位置していることを前提にご覧ください。
また、当社に寄せられた復元解答の得点状況と実際の全受験者の得点状況には大なり小なりの乖離が生じていることが考えられますので、今回の予想基準の中で示した合格予想基準等の確率等の数字については、あくまでも参考としてご覧ください。
※この合格予想基準は、当センター独自の見解です。それについてのお問い合わせ等は承っておりませんので、ご了承ください。
択一式試験
最近5年間の試験と比較した問題の難易度
寄せられた復元解答の採点による「択一式」の科目別及び全科目の総合平均点は、次表のとおりです。
なお、参考までに、令和2年(第52回)から令和6年(第56回)までの試験の得点状況もあわせて掲載いたします。
| 労基法 | 労災法 | 雇用法 | 一般常識 | 健保法 | 厚年法 | 国年法 | 総合点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 6.4 | 6.6 | 5.2 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 42.6 |
| 令和6年 | 6.5 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 7.3 | 7.6 | 43.1 |
| 令和5年 | 5.7 | 5.5 | 6.7 | 5.9 | 6.6 | 5.5 | 7.9 | 43.8 |
| 令和4年 | 6.3 | 5.6 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 43.7 |
| 令和3年 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 7.0 | 43.6 |
| 令和2年 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 43.8 |
今回の復元解答の択一式の総合得点の平均点は「42.6点」でした。 この得点は、前年(令和6年・43.1点)の平均点と比較すると、「0.5点」低下しており、過去5年間の平均点と比較しても最も低い得点でした。
択一式の合格予想基準
平成10年以降の択一式の総合得点の「合格基準点」は、その年の受験者の得点状況により、「41点」(平成18年)から「50点」(平成11年)の範囲で決定されています。
復元解答の択一式の総合得点の平均点とその年の「合格基準点」の関係を見ると、次表のとおりです。
| 復元解答平均点 | 合格基準点 | |
|---|---|---|
| 令和7年 | 42.6 | ? |
| 令和6年 | 43.1 | 44 |
| 令和5年 | 43.8 | 45 |
| 令和4年 | 43.7 | 44 |
| 令和3年 | 43.6 | 45 |
| 令和2年 | 43.8 | 44 |
平成20年以降の択一式の総合得点の合格基準点は、上表にはない平成20年〜平成29年を含めてみると、復元解答の平均点を3.3点上回って決定された平成27年及び平均点を1.6点下回って決定された平成30年を除き、 概ね復元解答の平均点と同じか、又は平均点を1点上回る得点で決定されています。 今回の復元解答の平均点は「42.6点」でしたので、この流れでいくと仮定した場合、今年の択一式の総合得点の「合格基準点」は、まず、「43点〜44点」の範囲の得点が考えられます。
なお、平成23年以降、平成30年までの8回の試験における択一式の合格基準点の推移をみると、平成28年(42点)を除き、7回までが「45点」又は「46点」で決定されていました。 難問が多かった令和元年の試験では、「43点」まで引き下げられましたが、今回の復元解答の平均点と比較して「0.5点〜1.2点」高かった令和2年〜令和6年の直近の5年間の試験では、 それぞれ、「44点」、「45点」、「44点」、「45点」、「44点」で決定されています。
択一式の合格基準点は、その年の「合格率」に直結しますが、直近の5年間の合格率が5〜7%台であったことから、今年の合格率が5%を下回ることは考え難く、 得点状況が直近の5年間の平均得点より低かった今回の合格基準点が、「45点」まで引き上げられる可能性はそれほど高くないと考えられます。
このように、直近5年間の平均得点と合格基準点との比較から、今回の択一式の合格基準点は、前述のように、「43点〜44点」の範囲の得点で決定される可能性が高いものと考えられます。
なお、択一式試験に合格するためには、総合得点だけでなく、科目別の「最低得点」(原則として「4点」)を確保することが必要です。 ただし、科目別の「最低得点」の「4点」は、特に受験者全体の得点が低い科目があった年は、その科目に限り「3点」まで引き下げられることがあり、 過去には、平成29年に「厚生年金保険法」で、平成28年に「一般常識」、「厚生年金保険法」及び「国民年金法」の3科目で「3点」の救済が行われています。 しかし、平成30年以降、直近の令和6年まで、救済措置が取られた科目はなく、また今回の試験では極端に平均点の低い科目もありませんでしたので、 今回の試験で「3点」の救済措置がとられる可能性はほぼないものと考えられます。
選択式試験
過去の試験と比較した問題の難易度
復元解答の採点(1科目5点満点、全科目40点満点)による「選択式」の「平均点」は次表のとおりです。
<選択式「科目別」・「総合得点」の平均点>| 基安法 | 労災法 | 雇用法 | 労働常識 | 社保常識 | 健保法 | 厚年法 | 国年法 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 3.3 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 29.7 |
今回の選択式試験の復元解答の総合得点の平均点は「29.7点」で、直近の3年間の平均点(令和6年・30.5点、令和5年・30.3点、令和4年・30.4点)よりおよそ0.7点低い得点になっています。また、科目別の「得点分布」は、次表のとおりです。
<選択式「科目別」の得点分布(%)>| 得点区分 | 基安法 | 労災法 | 雇用法 | 労働常識 | 社保常識 | 健保法 | 厚年法 | 国年法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5点 | 18 | 8 | 45 | 5 | 8 | 65 | 20 | 8 |
| 4点 | 46 | 37 | 32 | 29 | 38 | 26 | 48 | 43 |
| 3点 | 30 | 38 | 20 | 42 | 38 | 9 | 30 | 38 |
| 2点 | 6 | 14 | 4 | 20 | 12 | 1 | 2 | 9 |
| 1点 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 0点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後記で述べるように、「選択式」の科目別の合格基準は、原則として「全科目について「3点」以上(5点満点)の得点があること」とされています。
今回の試験で、原則的な「合格基準点」である「3点以上」の得点者の割合を科目別にみると次表のとおりです。 なお、参考までに、平成22年以降の同条件の得点者の割合もあわせて表に掲示します。
<選択式「3点」以上の得点者の割合(%)>| 基安法 | 労災法 | 雇用法 | 労働常識 | 社保常識 | 健保法 | 厚年法 | 国年法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 94 | 83 | 96 | 76 | 84 | 99 | 97 | 89 |
| 令和6年 | 93 | 97 | 94 | 68 | 92 | 87 | 92 | 91 |
| 令和5年 | 96 | 100 | 82 | 84 | 92 | 96 | 82 | 86 |
| 令和4年 | 99 | 88 | 94 | 88 | 70 | 97 | 92 | 98 |
| 令和3年 | 90 | 93 | 76 | 21 | 76 | 93 | 84 | 75 |
| 令和2年 | 88 | 98 | 99 | 46 | 74 | 84 | 98 | 93 |
| 令和元年 | 98 | 99 | 98 | 80 | 43 | 90 | 95 | 98 |
| 平成30年 | 80 | 98 | 95 | 68 | 85 | 91 | 83 | 65 |
| 平成29年 | 98 | 99 | 92 | 71 | 91 | 61 | 95 | 91 |
| 平成28年 | 94 | 98 | 68 | 42 | 84 | 85 | 76 | 82 |
| 平成27年 | 92 | 63 | 89 | 29 | 79 | 72 | 83 | 77 |
| 平成26年 | 96 | 91 | 92 | 82 | 94 | 88 | 93 | 99 |
| 平成25年 | 93 | 27 | 94 | 89 | 31 | 39 | 91 | 97 |
| 平成24年 | 98 | 99 | 83 | 94 | 61 | 81 | 66 | 94 |
| 平成23年 | 94 | 51 | 90 | 71 | 51 | 91 | 80 | 77 |
| 平成22年 | 91 | 89 | 94 | 91 | 59 | 78 | 55 | 28 |
選択式の合格予想基準
「選択式試験」は、平成12年から採用された出題形式ですが、直近10年間の合格基準は次表のとおりです。
<選択式「合格基準」>| 科目別得点 | 総合得点 | |
|---|---|---|
| 令和6年 | 「労働の常識」のみ「2点」以上。その他の7問は「3点」以上。 | 「25点」以上 |
| 令和5年 | 全問「3点」以上。 | 「26点」以上 |
| 令和4年 | 全問「3点」以上。 | 「27点」以上 |
| 令和3年 | 「労働の常識」は「1点」以上。「国民年金法」は「2点」以上。その他の6問は「3点」以上。 | 「24点」以上 |
| 令和2年 | 「労働の常識」「社会の常識」「健康保険法」の3問は「2点」以上。その他の5問は「3点」以上。 | 「25点」以上 |
| 令和元年 | 「社会の常識」のみ「2点」以上。その他の7問は「3点」以上。 | 「26点」以上 |
| 平成30年 | 「社会の常識」「国民年金法」の2問は「2点」以上。その他の6問は「3点」以上。 | 「23点」以上 |
| 平成29年 | 「雇用保険法」「健康保険法」の2問は「2点」以上。その他の6問は「3点」以上。 | 「24点」以上 |
| 平成28年 | 「労働の常識」「健康保険法」の2問は「2点」以上。その他の6問は「3点」以上。 | 「23点」以上 |
| 平成27年 | 「労働の常識」「社会の常識」「健康保険法」「厚生年金保険法」の4問は「2点」以上。その他の4問は「3点」以上。 | 「21点」以上 |
上の表でみるように、直近10年間の選択式の「総合得点の合格基準点」は、「21点〜27点」の範囲で決定されています。今回の選択式の平均点は、 「29.7点」でしたが、他の年度の平均点とその年の合格基準点との比較から、 今回の「総合得点の合格基準点」は、「24点〜25点」の範囲で決定される可能性が高いと考えられます。
なお、各問の合格基準点は、原則として、「3点以上」を合格点としていますが、上表及び前記の<選択式「3点」以上の得点者の割合>の表を比較すると、 「3点以上」の得点者の割合が特に低かった科目については、「2点」(さらに「2点以上」の得点者の割合の低かった科目については、「1点」)の得点を救済しています。
今回の選択式試験は、「労災保険法」、「労働に関する一般常識」、「社会保険に関する一般常識」以外の5科目については、「3点以上」の得点者の割合が「89%〜99%」と高く、これらの7科目については、「2点」の救済措置が行われる可能性は低いと考えられます。
今回、唯一「3点以上の得点者の割合」が80%を下回った(76%)「労働に関する一般常識」については、「5割」程度の確率で「2点」の救済措置が行われる可能性が考えられます。
また、「3点以上の得点者」の割合」が85%を下回った「労災保険法」(83%)及び「社会保険に関する一般常識(84%)」については、
それぞれ、「3割」程度の確率で「2点」の救済が行われる可能性が考えられます。
なお、前述の『選択式「3点」以上の得点者の割合』のデータについては、実際には、当社に寄せられた「復元解答」の傾向と受験者全体の傾向との間で少なからず乖離が見られるところです。 このため、前述の「2点」の救済措置の対象科目・確率等の内容については、このような「不確定要素」が残るものであることをご承知下さい。